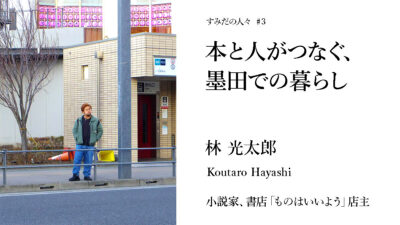目次
アパレルブランドをクライアントに持つ、ニット素材のカットソーを専門としたアパレルOEM企業、KIPS株式会社(以下、キップス)。主にアパレル製品の製造業を営みながら、専務取締役の田中康雄さんが率先して可能性の幅を広げています。ワークウェアブランド「KIPS works(キップスワークス)」の立ち上げや、自身の風呂好きが高じて始めたオリジナルの銭湯&サウナブランド「Off-low-buff-companys(オフローバフカンパニーズ)」、刺繍の技法を用いたインテリアプロダクト制作「ReVessel(リベーセル)」。さらに墨田区で家業を持ち挑戦している方にフォーカスし、新規事業や取り組み事例、家業ヒストリーのご紹介をする継創(つぎづくり)プロジェクトへの立ち上げに関わる等。さまざまな積極的な取り組みを「別の領域への種まき」と表現する田中さん。第2回目の「すみだの人々」では、そんな田中さんから詳しくお伺いしていきます。
予期せぬはじまり

田中さんがキップスに入社した背景には、家族の予期せぬ事情がありました。
「前の社長が叔父だったのですが、体調を崩してしまいまして、当時の専務だった父が急遽、社長に就任することになりました。親族内で手伝いできる人ということで、ぼくに声がかかったんです。ぼくの場合、やりたい仕事かどうか考える余地もなく、何の準備もないまま後継者となりました。家業を継いだ実感がないまま始まったんです。こう見えて後継ぎなんです(笑)。
今は父が社長をしていますが、代々田中家がこの会社を引き継いできました。ただ、うちの父は次男だったので、もともと継ぐ予定はなかったんです。ぼくは服飾系の専門学校には通わず、外の世界で就職していたんですが、叔父が倒れて急遽会社に入らなければならなくなったことが転機でした。」
キップスの創業は、田中さんの曽祖父の代にまで遡ります。元々の名前は「田中メリヤス製造所」。創業してから100年以上もの間、ニット素材のカットソーに向き合ってきた老舗の会社。昭和63年にキップス株式会社に屋号を改めます。田中さんは、その名前の由来について教えてくれました。
「元々うちはキッズ服とかベビー服とかの製造をやっていました。KIDS IDENTITY PLANNING SUPPORTの略でキップス(KIPS)なんです。今はキッズをやっていなくてレディースに移行したので、ニット(KNIT)の頭文字のKで。KNIT IDENTITY PLANNING SUPPORTの略ですね。」

––田中さんご自身がキップスに参加されたのはいつ頃だったのですか
「2014年ですかね、ちょうど10年前でした。ぼくは前職がコンタクトレンズの販売業の企業だったんです。新卒でそこで働いていました。」
––田中さんは生まれも育ちもずっと墨田ですか?
「そう、ずっと墨田なんです。でも中学から受験して外に行っているんで小学校の同級生以上は墨田の方々と全く縁がなかったんです。会社を継ぐことになって墨田区の事業後継者の為のビジネススクール『フロンティアすみだ塾』で関係を築いていきました。そもそもうちが両国駅前にある「東京ニットファッション工業組合」に所属しているんです。この辺一帯に同業も多く、青年部に息子さんが入ったならどうぞって言われて、、、。青年部といってもこのご時世、後継ぎも少ないので50歳くらいまで。青年の幅が広いんです(笑)。ただコミュニティに所属するのは最初消極的でしたし、おじさんたちの話を聞いて何がたのしいのかなと思って断っていたんです。2、3年経って当時の委員長から『今度飲み行きませんか』ってまた電話がかかってきたんです。さすがにこれは逃げられないやとなって勧誘を受けて足を運んだら全然怖い人たちでもなく、同業だけど仲間意識が強くて学ぶ機会もあっていいなって思い直したんですよ。その青年部のお兄さんの中にフロンティアすみだ塾の卒業生がいてこっち入ったらと言われてすみだ塾や商工会も進められて入って、どんどんコミュニティが増えていきました。」

外に向けて種をまく
現在、KIPSの従業員数は福島の工場を含めて約30名。そのうち8名はベトナムからの研修生で、地元の高齢の従業員が中心となっています。「業界全体が高齢化しているため、平均年齢は60歳ほど。生産効率は年々落ちてきています」と田中さん。
—では生産効率が落ちていったところから自社ブランドの立ち上げを?
「いやそこからはあまり繋がってなくて。こだわりはないものの会社に入ってみると、改めて服は割と好きな方なんだなと気づきました。今は役員にもなっていて、そうなると、もちろん責任は問われるんですけど、ある程度仕事の業務的な内容、時間制限というところで自由度が生まれてくる。そんな中で主軸のビジネス以外でもなんかちょっとでも動けることがあったらなというところで探していた時にいろんなひとと出会って一気にコミュニティが広がっていきました。それが最初に仲間内でやっていた作業着をいっしょに作らせてもらうという案件からキップスワークスというブランドが始まりました。」

––田中さんからお仲間が広がった感じですかね
「そうなりますね。あんまり従業員さんは起用せず、ぼくの時間を使ってやっています、本業に弊害が出てはいけないので。役員の労働時間なんてあってないようなもんじゃないですか。残業しようが関係ない。自分の時間を使ってなるべく本業に支障でないようにして進展していっている感じです。」
––面白いところもありますけど、本業のベースがあるからこういうのもしっかりできる感じですよね
「アパレルは全体的に斜陽産業って言われているんですよ。服が売れないとか、なかなか商売としても難しいところがあり、業種的にアパレル業界でずっとやっていこうとはぼく自身思っていないんです。そういう意味で、今ぼくのしているプロジェクトは種まき。外の別の畑に対する種まきをしているって感じです。今はまだ本業は続けていかなきゃならないし、右肩下がりにはなっているけど工場もあるし、人員もいるのでいきなりばっとかえることはできません。徐々にスライドさせるイメージで収益の分散をさせながらウェイトを変えていければいいかなとは考えているんです。」
––さきほどの福島の工場は分社化しているんですか
「はい。法人がちがいます。ただ代表は父で完全に子会社で。社長はしょっちゅう行ってますけど、ぼくは年に2、3回工場を行き来しつつという程度です。鮫川村っていうところに工場はあるんですけど、初めて鮫川村役場に行きました。人口2000人レベルの村で村役場の副村長さんやほかの村民の方とも知り合いが多いんですけど。福島県が主催するテントサウナイベントをキャンプ場があるそこの村でやることが決まって。ぼくの持っているオフローバフカンパニーズというブランドとコラボすることになったんです。うちのブランドを使いながらダブルネームでイベントを盛り上げるじゃないですけど、友だちを連れて行ってそういうところからチームで仲良くなったら、今、継創という事業継承のトークイベントもやっているのでこのメンツを鮫川村と繋げるとかも検討しているんですよね。継創は墨田区の産業観光も目指してやっているので、流れを考えながら進めていきたいです。」


「点」を「線」でつなぎ、さらに「面」へと広げていくアプローチ
––実際、田中さんの活動は広がっていて、イタリアのミラノサローネにも自社のカットソーを使ったフラワーベースをデザイナーさんの協力を得てリベーセルとして出品。世界基準の評判もあったり、アパレルの領域を飛び越えたインテリア業界への領域も見据えています。この商品のアイデアの始まりは田中さんの中から出てきたものがやっぱり多いんですか?
「これに関しては7、8割くらいデザイナーさんからの『こんなことできますか』っていうのが大きいです。ぼくの意向としては別の畑にいきたい。そんななかで親和性があってぼく個人としても興味があった領域だったのがインテリアでした。家業も布を扱う仕事なので、衣食住あたりは親和性あるので、進んでいきやすい領域かなというのもあったり、ぼくもインテリア見るの好きだったりして。あのあこがれのお店にうちの商品が並ぶのがいいなっていうのを考えながらデザイナーさんとそういうアイテムを作れたらうれしいですと相談させてもらって。うちがずっと婦人服を作ってきた会社なので、パフスリーブみたいな丸い袖の感じ。今までうちがやってきたミシンの始末だったりとかそこに少し関連づけられるアイテムだとよりいいですという話をしたときにデザイナーさんにラフを持ってきていただいて。ワインボトルの花瓶のラフデザインをみたときにこれがいちばんいいかなと。でルーツとしても、うちの母親がフラワーアレンジメントを趣味でやってて、うちの父親がワインが好きだったりで『じゃあこれでいきましょう』とフラワーベースを選んだってことだったんです。」


––ストーリーもしっかり乗っかっていて、ストンと腹落ちしました。
「ありがとうございます。先ほどのオフローバフカンパニーズの場合はコミックブランドをイメージしていて、ぼくの趣味を割と多めに反映しているところがあります。名前にはオフとローが入っているんですけど、こういうぼくみたいな人間ってプライベートと仕事の境目がないもんで、家庭と仕事がいっしょになっちゃうんです。そういう意味でも銭湯が好きだったし、この辺下町で銭湯文化も根付いているし。そういうところにいって無理やりスイッチを切り替えるっていうことをブランド化したいなと思ってこのブランドが出来上がりました。
中小企業の仲間同士で話していてもよく感じるのですが、後継者というのは業種を選ぶことができません。だったらその範囲内でどんなことができるかを打ち出していけたらと思って始めましたんです。」

––キップスワークスとかもそういう始まりから?
「はい。うちの苦手な分野からいうと、シャツやジャケットは作れないんです。町工場のいわゆるみなさんがイメージされる襟付きの作業着っぽい作業着は作れなくて。うちはパーカーとかTシャツ。いわゆるカットソーと呼ばれるカジュアルウェアをメインに作っていて。そっちじゃないと作れないという領域があります。ただありがたいことにいろんなご縁があって、社長さんやお店の店主さんとかと話す機会が増えているので、いろんな業種の話が聞けて。仲良くなると工場見学もさせてもらえて。そんな中で 『ツバメ研磨工業所』さんとかは有名なファストファッションのTシャツを着てて、作業員さんの服の同じ箇所に穴が空いているところに着目しました。工場を案内されると窓もなくて暑い環境下でお仕事されてて。金属加工の作業はみんな同じ位置に穴があくなら、穴が空きにくい生地があるからそれをあてがってあげよう。窓がなくて熱いなら吸水速乾の生地がいいなとか。『みんな腕をまくっているけど、ほんと腕をまくると危ないんだよね』とポロッと出たことばにリブの部分を長くしてぴたっとさせるのはどうだろうとかアイデアも湧いてきて。このアイデアを持ち帰ったんです。デザイナーじゃないからデザインはできないんですけど、機能性をいろいろ盛り込んで形にしたら機能美になると思いました。それがロンTっぽいものになって評判もよかったんです。結果的に作業着っぽくなくてカジュアルでかっこよくなったという声も聞けて従業員さんの満足度もあがった。いい意味で作業着っぽくなくなって普段着づかいしたいと言ってもらえてそれはカットソーの強みだよなと捉え直しもありました。」


––コミュニケーションから今ある不都合を解決しているんですね。
「作業着って基本カタログベースで選んで、あれはあれで汎用性はいいんですけど、一社特化型でインタビューしてぼくだけが感じ取ったことをアイテムに落とし込んでコンサルみたいな形でオーダーでやっていたら大手にはできない動きなんですよね。中小企業だから枚数はそんなに出ない小ロットですし。ぼくの時間をめちゃめちゃ使うから金額にあっているかわからないですけど、これができたら唯一無二だよなって思っています。また墨田区っていろんな業種があるんで、どんどん続けていったらいろんな業種のデータが集められるんです。じゃあ金属加工特化型のワークウェアとうたっても面白いし、そうなった場合に新潟の燕三条市の産業にも持っていけるとも思いますし。墨田区の点を地方に広げるっていうこともできるし、これは面白いプロジェクトだからキップスワークスというブランド化しようとなったんです。あくまでどのアイテムがブランドっていうわけではなくてこうやって作る。インタビューして、現場に張り付いて見つけてアイデア出してお話をして出てくる、このやり方をブランドにしようとやっていったら周りから『よかったよ』といってもらえるようになって。よりこういうことをしていると仕様が複雑になるので、それを工場にやらせた方がより腕も上がるんで。技術だって結果的に工場に還元できるので、良い取り組みかなと思っているんです。」
––めちゃくちゃ戦略的な話ですね。これだけだとわからないけど、話を聞いてみるといろいろ田中さんならではの考えが理解できます。
「それを全部うちがやる理由があって、キップスか、もしくはキップスの田中康雄がやる理由がある、というのをちゃんと線を引きながら本業に対してリンクするような接点をつくるようにしているんです。ぼくのイメージでは本業があって、その周りにいくつか点が打たれていて、線でつないでメッシュ、蜘蛛の巣状に広げていく。そうするといろんな入り口を作っていく感覚で、今まではTシャツ作れる会社ですという一個の玄関口だったものが他から作業着も作れる会社なんだとか。入り口を周りに増やしていって、裏口からも入れるようにする感覚ですね。」
––流入口をたくさん作るイメージですよね。今みたいな話を町工場で困っている人や第二創業者の方たちにも聞いてもらいたいなって思います
「新しいことにチャレンジするとか次の布石を打つとかはアンテナを広げてやっていこうと意識しています。」
––これを聞くと意味がよりわかりますね。面白いです
「お風呂のブランドやりました。インテリア系のフラワーベースをやりました、ワークウェアブランドも、継創もですね。ぜんぶ独立しているんですけど、別軸で独立してやり始めていて。ぼくが自社プレゼンを他社の方に話す時ってちょっと困るんですけど、やることが多くてこの人結局なにしているんだってなるんです。ぼくの説明が足りてない部分もあるんですけど、今話したみたいに必ずやった理由がちゃんとあって、うちがこうだから始めたという。逆にいうとうちがやる理由がないものはやらないようにしているんです。それぞれ離れたところに独立したところに点を打っていってます。」
新しい挑戦と未来への期待
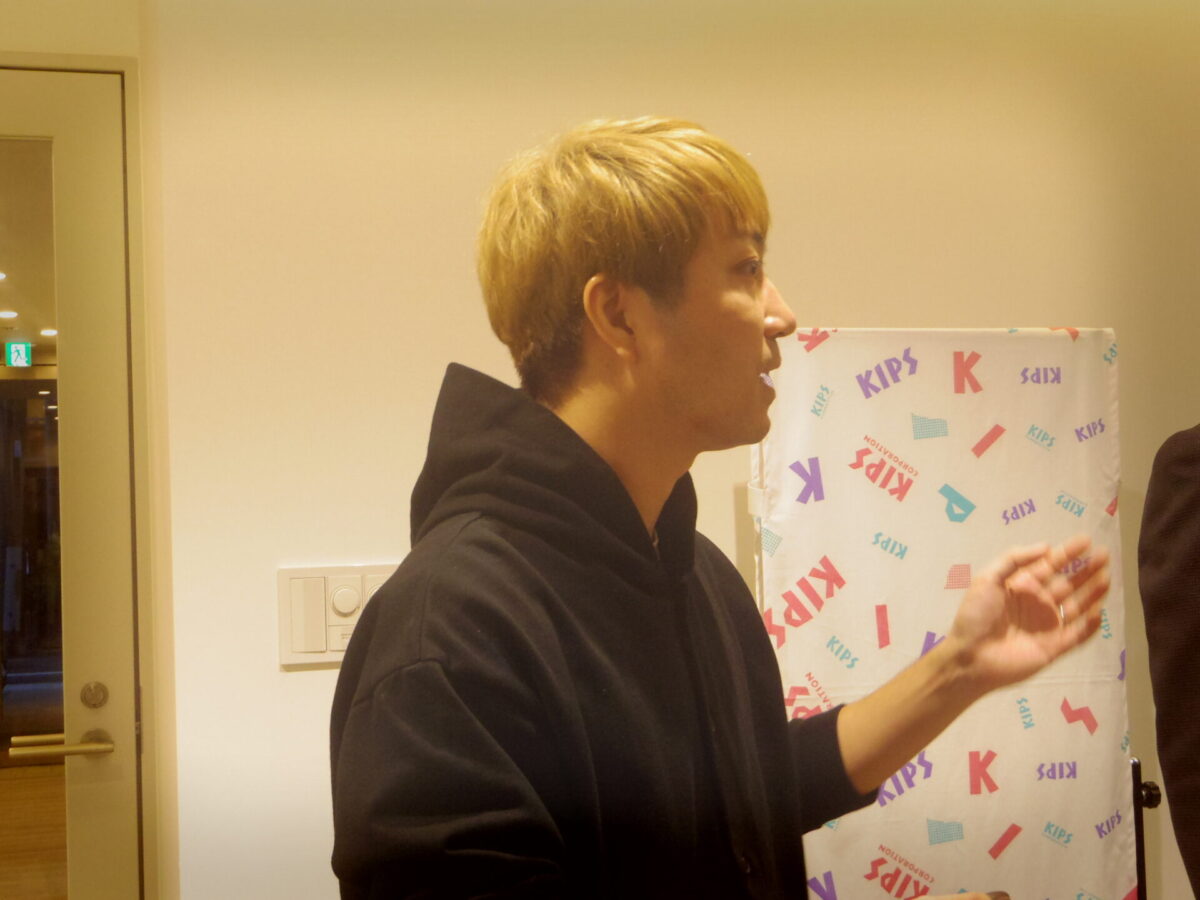
田中さんが多くのプロジェクトに挑戦する考えに至った背景には、フロンティアすみだ塾卒業後のある出会いがありました。「松山油脂の社長さんのお話を聞く機会があって、そこから大きなヒントを得ました。松山油脂さんも外部から後継ぎとして入られた方で、『自分がやりたい領域に生産背景をスライドさせる』という考え方を共有されていたんです。そのスライドという発想に感銘を受けました」と田中さんは語ります。
「いきなり大きく変革するのではなく、既存の技術や人材、資金を活用しながら新しい領域に少しずつ移行する。これが非常に現実的で、挑戦する上での大きな指針となりました。その話を聞いて、改めて『自分がやりたい領域は何か』を見直すきっかけになったんです」
––またそういうのができる業種っていうのもよかったですよね
「そうですね。特に洋服とくくると制限されるんですけど、解釈を広げて布を扱う仕事というか、業種を素因数分解の形にしてもいいかもしれない。切るだけの仕事、ミシンを踏みます。針を扱うだけの仕事でも良いかもしれない。そう考えたときに布というのが素材としていろいろなものとの親和性が高い。そういうのを感じた時に他の畑に行きやすいっていうのは感じていて業種的な武器だなって思っています。」
––最後にこれからのこともお伺いしてもいいですか。
「さっきの工場のある鮫川村での話で、役場の方とまずどんなことしましょうかねという話から方向性が決まったんです。農林商工課、次に、むらづくり振興課。どんどん名刺配りしていって、関係人口として『今度イベントをやっていってください』と言われてぼくも気づいたんです。たしかに鮫川村にとってぼくは関係人口の一員になるのかなって。
長いスパンで見たとき、過疎化が進む村でぼくたちの工場を存続させていくには、人を雇用する方法として、規模的にも『地方創生』くらいの大きな気持ちで取り組まなければ難しいと思っています。村への誘致や、Iターン・Uターン、新規に他地域から人を呼び込むといった取り組みが必要です。ただ、こうした人材の取り合いが激化する中では、行政と協力して、たとえばオープンファクトリーのような仕組みを作るのも一つの方法です。
産業が観光地として注目されることで、産業観光という形で盛り上がり、最終的に人口増加につながることを目指した方が良いと思っています。採用活動を進める上でも、こうした取り組みが必要です。そこで、ゴールを見据えた際に、今のうちから自分自身が関係人口の一員となることが大切だと感じました。鮫川村でのぼくの動き方についてももっとしっかり考えて取り組んでいかなければならないと、最近強く思っています。」
––さきほどの鮫川村とオフローバフカンパニーズのコラボ企画は第一弾だったんですよね。
「そうなんです。あとはこれからの動きとして今年、本社を建て直しました。このフロアはその一環で、家庭のリビングのように、ほっとくつろげるスペースになっています。普段は打ち合わせ用の会議室として利用していますが、近隣の事業者向けに展示会や写真撮影用のスペースとしてもレンタルしています。利用方法に制限はなく、業種もアパレルに限らず、どなたでも気軽にご利用いただけます。
例えば、アパレルの場合、レンタルオフィスとかマンションの一室を借りて展示会を行うのが一般的ですが、そんなときにこのスペースを活用していただければと思います。この場所で商談がまとまったり、他の事業者とのつながりが生まれたりして、そこからコラボレーションが広がる場になれば嬉しいです。ぼくもできる限りお手伝いしますので、どうぞ気軽にご相談ください。」


田中 康雄
KIPS株式会社 専務取締役
立教大学法学部を卒業後、新卒で医療機器販売会社に入社。約3年程勤務後、キップス株式会社に入社。本業の傍ら、キップスワークスやオフローバフカンパニーズ、リベーセルを運用中。墨田区の家業仲間と継創(つぎづくり)プロジェクトを立ち上げる。